フューチャーセンター(Future Center)とは、多様な人たちが集まり複雑化したテーマ(課題)について「未来志向」、「未来の価値の創造」といった視点から議論する「対話の場」のことを指します。岐阜大学ではこのような地域との対話を創発するためのフューチャーセンターや多様な人との交流ができる空間を構築・運営し、地域との「協学」を推進します。
①地域との対話を通して地域が直面している複雑・広範化した課題の解決に向けて取り組みます。
②フューチャーセンターを活用し、社会貢献に取り組みます。
・産業への貢献:研究主体から学生・生涯教育を含めた地域課題解決を目指します。
・地域政策への貢献:地域課題を浮き彫りにし、地域と協学しながら解決するという循環を創出します。
・地域教育と文化への貢献:地域をめぐる「学び」の仕組みを作り、地域住民が自らの地域課題に即して行政と協働して解決し得るよう支援します。
他国のまちづくりを学び
新たな視点で地域を見つめる

5月22日、飛騨高山まちの博物館において、「ひとのつながりから地域をつくる」をテーマにぎふフューチャーセンターを開催し、岐阜大学生、高山西高校及び飛騨高山高校の生徒、高山市民のほか国内外のソーシャル・キャピタル(社会関係資本)の研究者が参加しました。
対話の前に、スウェーデンのハンス・ウェストランド教授から同国の地域活性化の事例の紹介があり、参加者は地域の取り組みを成功に導くためには、ひととのつながりや起業家精神が大切であることを学びました。対話では、最初に「自分の身の回りと比較して、スウェーデンの事例で感じたこと」について話し合い、次に「高山をモデルとして、地域で出来ること」について意見やアイデアを交換しました。
高山市の活性化には、行政と企業を協力させる仲介役が必要であること、地域をあげた起業家育成の必要性、高校生が自ら国際的感覚を身に付けるなどの意見が出されたほか、ハンス教授らが出席した国際研究会において今回の対話の内容が報告されました。
各グループからの意見・アイデア
・高山の魅力をつくるためには若い人が定住することが重要で,若い人が高山のいいところを発見したり、地元に帰ってくる仕組みをつくることが必要
・飛騨牛を世界に広めるために、高山の助け合いを大切にする地域性を生かして、起業をする
・高山の人たちの『ぬくい』人間性は地域の良さであり、高齢者に優しく若者に楽しいまちをつくる
・物事を起こすときに、地域の協力体制やまわりの資源を活用することが大切
 |  |  |
 |
違う視点からみるきっかけに フューチャーセンターのはじまりはスウェーデンですが、多くの高校生と対話をする機会は今回が初めてでした。話題提供として、ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)やアントレプレナーシップ(起業家精神)をキーワードに話をしました。難しい言葉ですが、それぞれの立場で解釈することで高山を違った視点から見るきっかけになったと思います。
|
岐阜大学×揖斐高校 いびの魅力を世界へ発信 6月5日、揖斐高校と岐阜大学が連携して開催した「自然豊かないびワクワクフューチャーセンター(略称:いびワクフューチャーセンター)」には、揖斐高校生活環境科の生徒(いびっ高隊)、岐阜大学生、揖斐川町の皆さんら58人が「いびの恵みの発信~効果的な発信方法を考える~」をテーマに対話しました。高校生がグループのリーダーを務め、大学生はそのサポートを行いながら、いびのいいところ(いびの恵み)やその発信方法について意見を出しながら対話を深め、最後に「いびの恵みをもっと世界へ発信するには」としてまとめました。各グループからは「揖斐のアイドルをつくる」、「いびがわマラソンを通じた国際交流」、「揖斐のブランド化を進める」、「揖斐茶のPR強化」などの意見が出されました。

揖斐高校では、対話で出された意見を活かし、揖斐川町の広報活動や特産品を生かした製品づくり(揖斐茶のクッキー、草木染の着物など)を行っています。フューチャーセンターをはじめとする揖斐高校の活動について、岐阜大学は今後も連携して取り組んでいきます。
各グループからの意見・アイデア
・揖斐のアイドルをつくる
・いびがわマラソンを通じた国際交流
・オリンピックなど国際的な大会の開催
・揖斐(揖斐川)のブランド化を進める
・揖斐茶のPR強化
・高校生が特産品を考え、地元企業と協力して売り出す
・空港をつくる
 |  |  |
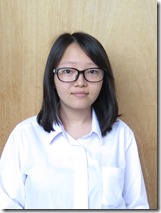 |
いびっ高隊で情報発信 グループでの話し合いは事前研修で経験したこともあり、スムーズにできました。大学生や社会人の方の自分とは違う考え方を知り、刺激になりました。 高校生がクッキーを考え、特産物として売り出すのは地域の活性化につながると思います。今後もいびっ高隊全員で揖斐川町のことを発信していきます。
|
FC通信Vol.18のPDFはこちら↓
| 2025.12.08 | |
| 2025.12.03 | |
| 2025.11.17 |
令和7年度岐阜大学公開講座 SDGs×地(知)の拠点 「大学と博物館の協働による地域づくりの可能性」を開催します。12月6日(土) |
| 2025.11.06 | |
| 2025.10.06 |