フューチャーセンター(Future Center)とは、多様な人たちが集まり複雑化したテーマ(課題)について「未来志向」、「未来の価値の創造」といった視点から議論する「対話の場」のことを指します。岐阜大学ではこのような地域との対話を創発するためのフューチャーセンターや多様な人との交流ができる空間を構築・運営し、地域との「協学」を推進します。
①地域との対話を通して地域が直面している複雑・広範化した課題の解決に向けて取り組みます。
②フューチャーセンターを活用し、社会貢献に取り組みます。
・産業への貢献:研究主体から学生・生涯教育を含めた地域課題解決を目指します。
・地域政策への貢献:地域課題を浮き彫りにし、地域と協学しながら解決するという循環を創出します。
・地域教育と文化への貢献:地域をめぐる「学び」の仕組みを作り、地域住民が自らの地域課題に即して行政と協働して解決し得るよう支援します。
ぎふフューチャーセンターは、大学、地域、自治体がともに地域の課題を探り、未来に向かって新しい価値をつくる対話の場で、岐阜大学の地(知)の拠点整備事業の取り組みの一つです。今年度の13回目は、岐阜大学と岐阜県の共同開催で、県が提案したテーマについて、学生、地域住民、行政職員の皆さん29人が話し合いました。
生物多様性保全に向けて

自然との関わり方をともに考える
私たちの暮らしは、多様な生きものが関わり合う生態系から得られる恵みによって支えられています。この生物多様性について学生、地域住民、行政職員がともに考えるため、平成27年2月23日、「生物多様性について考える~レッドデータと外来種問題~」をテーマに岐阜大学図書館ラーニングコモンズにて開催しました。
対話に入る前に、岐阜大学地域科学部向井貴彦准教授による講義のほか、岐阜県自然環境保全課の担当者が県の取り組みを紹介し、参加者が生物多様性について知識を共有しました。
司会進行は、岐阜大学地域協学センターの地域コーディネーターである野村典博さんが行い、まず、5、6人のグループになり自分にとっての身近な生き物について語りながら自己紹介し、「自分のまわりの生物とその環境の変化」について話し合いました。イノシシやニホンジカ、サルなどの増加で農作物に被害が出ていることやブラックバス、ヌートリア、アライグマ、アルゼンチンアリといった外来種が増加しているなどの意見が出されました。次のセッションでは「変化の原因は何か」について対話し、宅地開発や山・農地の手入れ不足などにより、生物が生息できる環境が減少していることがあげられました。
最後に「生物多様性保全に向けて、どのように関わっていくのか」について話し合い進め、各グループの代表から、外来種や有害な動物(イノシシ、シカ)を食べるよう消費活動を進める、生物多様性について知る・関心を持つ、子どもに伝える、自然の変化に合わせたルールを作るなどの意見が発表されました。
今回のフューチャーセンターを一つのきっかけとして、多くの人たちが身近な地域における生物多様性について、今後も「ともに考え続ける」ことが大切です。
各グループからの意見・アイデア
・ブラックバスなどの外来種や有害な動物(イノシシ、シカ)を食べる
・生物多様性について正しい知識を持つ
・生物や自然環境について自分の目で見て知る、関心を持つ
・カワゲラウォッチングなどを通じて子どもたちに伝える
 |  |  |
フューチャーセンターをPR
教育学部学生がポスターを作成!
フューチャーセンターをはじめとした岐阜大学の地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)について学内のみなさんにより知ってもらうため、教育学部美術教育講座3年生11人が、日頃の学習を生かし、共同でポスターを作成しました。
ポスターは、学生のノートをイメージしたもの、メッセージをクエスチョンマークの形にして大きく取り上げたものなど。アイデアとセンスの詰まったポスターは、今後、学内各所に掲示していきます。ぜひご覧ください。
 |
| 岐阜大学教育学部美術教育講座3年のみなさん |
 | 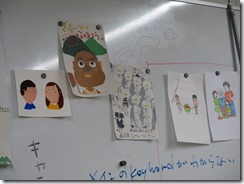 |  |
| 使用するイラストやイメージ、キャッチコピーを絞り込み | 各自が案を作成 | |
 | 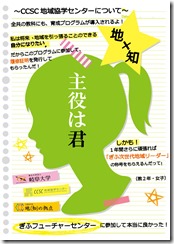 | |
| よりよくするための話し合い | ||
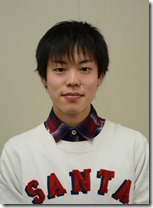 | 対話を通じて見聞を広めたい 参加前はフューチャーセンターのイメージがなかなか湧かず、グループで話し合いができるか不安でしたが、参加してみるとテーマに対する説明がわかりやすく、みなさんが気さくでとても話しやすい場でした。また、学生だけでなく、地域の方、行政職員の方とも同じ立場で意見交流ができて有意義な時間を過ごすことができました。社会人の方も私たち学生と同じ意見、疑問を持っていることに親近感を抱きました。今後も、このような対話や交流の場があったら積極的に参加して、見聞を広めたいと思います。
|
 | 様々な意見に触れる機会 私は以前、外来魚駆除の釣り大会に参加したこともあり、生物多様性について学生や地域のみなさんがどのような考えをお持ちなのか知りたいと思い参加しました。 対話では、「外来魚を食べて活用したらどうか」、「子どもたちへの環境教育が重要だ」などの提案があり、様々な意見に触れる機会となりました。今後の業務に活かしていきたいと思います。
|
FC通信Vol.17のPDFはこちら↓
(1.32MB)
| 2025.12.08 | |
| 2025.12.03 | |
| 2025.11.17 |
令和7年度岐阜大学公開講座 SDGs×地(知)の拠点 「大学と博物館の協働による地域づくりの可能性」を開催します。12月6日(土) |
| 2025.11.06 | |
| 2025.10.06 |