令和5年9月7日(木)に、養老町教育委員会生涯学習課主催の「養老町社会教育委員会 第1回自主研修会」にて、ぎふ地域学校協働活動センター事業のひとつである「市町村支援プログラム」を実施しました。参加者は、社会教育委員4名と地域の公民館長2名、養老町立広幡小学校教育支援コーディネーター1名の計7名でした。ぎふ地域学校協働活動センター員の後藤誠一(岐阜大学地域協学センター助教)による地域学校協働活動についての基礎的なレクチャーのあと、養老町教育委員会生涯学習課の細川誠氏から養老町の地域学校協働活動について情報提供があり、その後参加者全員で地域内にある取り組みを共有するワークを行いました。
参加者からは、「地域学校協働活動というと見慣れない言葉だが、実はすでに地域で取り組まれていることがたくさんあるのだと確認できた」という声が聞かれた一方、「地域学校協働活動というものを地域で周知するにはどうしたらよいか」、「活動の後継者がおらず困っている」といった具体的な困りごとの声も寄せられました。
ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後も養老町の方々と対話しながら、地域学校協働活動が持続的なかたちで促進されていくよう、伴走型の支援を行っていきます。
市町村支援プログラムとして「羽島郡地域学校協働活動研修会(岐南町・笠松町)」において講演会とワークショップを実施しました
令和5年8月30日(水)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業のひとつである市町村支援プログラムに基づき、岐南町中央公民館で開催された「令和5年度羽島郡地域学校協働活動研修会」に講師派遣を行いました。本研修会には、岐南町・笠松町の全8小中学校から、学校運営協議会委員や町内の教育委員、社会教育委員、地域学校協働活動推進員、社会教育士等の32名が参加しました。
はじめに、講師である多治見市立根本小学校校長 横山美智代氏より、「学校運営協議会を活かした地域学校協働活動の推進」というテーマで講演がありました。その後、4~5名程度の小グループに分かれてグループワークを行い、横山氏による支援のもとで「熟議」を体験しました。参加者の感想を一部紹介します。
「法的な根拠や具体的な事例をお話いただき、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動について、すっきり整理できた気がします。『熟議』を行うためのグループセッションの方法もよくわかりました」【学校運営協議会会長】
「私は地域の人間として学校運営協議会に参加しています。今後も地域とのつながりを大切にして、子どもたち、先生方、地域住民が自慢できる学校づくりに取り組んでいきたいと思います」【学校運営協議会委員】
「『熟議』を通して、目標・目的を共有することができることを学びました。子どもも大人も楽しみながら、子どもを真ん中にした地域と共にある学校づくりを、学校運営協議会を活かして進めていきたいという思いを強くしました」【小学校教頭】
「学校運営協議会において、共に育てたい子どもの姿について、改めて「熟議」してみたいと思いました。地域の方、保護者の思いを聞いて、どんなことができるのか考えたいと思いました」【小学校教頭】
ぎふ地域学校協働活動センターでは、次年度以降も当プログラム等を活用し、様々な活動に取り組んでいく予定です。
講演の様子 ワークショップの様子
令和5年度学校教職員向け「コミュニティ・スクール 地域学校協働活動」研修会を実施しました
令和5年8月3日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センターは、人材育成事業の一つである「教職員向けコミュニティ・スクール 地域学校協働活動研修」(以下、「教職員向け研修」)を実施しました。
ぎふ地域学校協働活動センターは、地域・自治体・学校における「地域学校協働活動」を支援・促進し、子どもたちの成長を地域全体で支えるととともに、活動を通じて地域の活性化を図ることを目的に、平成31年4月に岐阜県と岐阜大学の共同で設置されました。同センターは、①人材育成・確保、②調査研究、③普及促進を行っており、今回の教職員向け研修は①人材育成・確保に関する取り組みです。
今年度の教職員向け研修はオンラインで開催し、219名の受講がありました。受講者は、県内各地域の学校教職員、社会教育行政等で活躍している方々で、様々な課題意識をもって参加していました。
はじめに、益川浩一センター長から教職員向け研修の目的や概要を説明しました。次に、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 地域学校協働推進室 室長補佐 齊藤 陽介 氏から、「地域とともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりを目指して~コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進~」というテーマで講演がありました。講演では、先進的な多くの具体的事例を交えながら、学校運営協議会が想像する子どものあるべき姿を共有し、その姿を目指す目的や手段を明確にすることで、子どもたちの学びや生活をより豊かなものにすることができるなどの話がありました。
講演後には、質疑応答や受講者同士のグループ交流を行いました。地域学校協働活動推進員を軸に学校と家庭と地域がネットワークをもつことで、ふるさと学習や不登校支援、働き方改革などにも協働活動の幅を広げられるなどの助言が行われるなど、有意義な学びの機会となりました。
受講者の皆さんには、今回の研修で学んだことを生かし、社会に開かれた教育課程の実現に向けて、それぞれの学校で地域学校協働活動を推進されることを期待しています。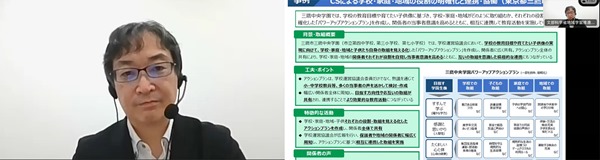
教職員向け研修の様子
自治体支援事業として、羽島市コミュニティ・スクール推進協議会において講演会を実施しました
令和5年8月25日(金)に、羽島市役所で、「令和5年度第1回羽島市コミュニティ・スクール推進協議会」を開催し、羽島市立幼稚園、羽島市立学校の学校運営協議会委員や、園長・学校長等の学校関係者49名を対象に、講演会を実施しました。
はじめに、岐阜市立岐阜小学校学校運営協議会の青山朋宏会長から、「いま なぜ コミュニティ・スクールなのか」と題したご講話をいただき、岐阜小学校の豊富な実践をご紹介と、これからの子どもたちに必要とされる非認知能力の育成には、地域の力が必要であるとのお話がありました。岐阜小学校では、できるだけ多くの「楽しい」体験や経験、様々な世代の人との「楽しい」ふれあいの場をつくるために、多岐にわたる活動が展開されています。
また、後半では、青山会長とぎふ地域学校協働活動センター長の益川浩一(岐阜大学地域協学センター長)との対談がありました。子どもにかかわるすべての人が願いを共有すること、岐阜小学校の「ふるさと大好き」のような共通のスローガンをもつことによって、学校が「地域を創造する場所」に近づいていくのではないかと、参加者と一緒に考えることができました。
羽島市は、学校運営協議会が設置されて7年目を迎えており、今後、子どもを中心としたコミュニティ・スクールに関わるすべての人が楽しめる在り方を検討していくことを期待しています。
自治体支援事業として、 美濃加茂市「地区連合PTA定期大会」において講演会を実施しました
令和5年7月28日(土)に美濃加茂市生涯学習センターで、美濃加茂市地区連合PTA定期大会が開催されました。
ぎふ地域学校協働活動センター長の益川浩一(岐阜大学地域協学センター長)を講師として、美濃加茂市内小中学校の管理職やPTA本部役員、学校運営協議会委員等、93名を対象に、「なぜ、今、学校・家庭・地域の連携・協働が大切なのか」を演題とした講演会を実施しました。
講演では、多様化・複雑化する地域や学校の課題に対応していくためにも、課題の解決に向けて学校・地域・家庭がパートナーとして連携・協働していくことが必要であることや、連携・協働はあくまでも「手段」であって、連携・協働のための組織を作ることや連携・協働することそのものは「目的」ではないこと等が話されました。
美濃加茂市では、令和4年度に市内(組合立も含む)12校すべての学校がコミュニティ・スクールとなりました。今回の研修を通して、各校の学校運営協議会で、願いの共有とともに「あるもの活かし」の発想で、これまで実践・蓄積してきた活動や地域の資源を洗い出し、課題や目的を明確にしたり、活動体制の在り方を検討したりすることで、活動が充実していくことが期待されます。
令和5年度第1回地域学校協働活動推進員等育成研修(全4回)を実施しました
令和5年6月29日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センターの人材育成事業の一つである「第1回地域学校協働活動推進員等育成研修」(以下、「育成研修」)を実施しました。
ぎふ地域学校協働活動センターは、地域・自治体・学校における「地域学校協働活動」を支援・促進し、子どもたちの成長を地域全体で支えるとともに、活動を通じて地域の活性化を図ることを目的に、岐阜県と岐阜大学の共同で設置されました。同センターは、①人材育成・確保、②調査研究、③普及促進を行っており、今回の育成研修は①人材育成・確保に関する取り組みです。
今年度は86名の受講申込がありました。受講者は、県内各地域の社会教育行政、公民館等の施設、学校、地域団体等で活躍している方々で、様々な課題意識をもって参加されていました。
育成研修はオンラインで開催し、宇都宮市(講師)、岐阜大学 (オンライン事務局)、受講者の自宅等をWeb会議システムで結んで実施しました。
益川浩一センター長から育成研修の目的や概要を説明したあと、一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事/元宇都宮大学教授 廣瀬隆人氏から、地域学校協働活動の概論として、地域学校協働活動やコミュニティ・スクール(学校運営協議会)をどのように捉えて実践していけばよいか、地域学校協働活動推進員の役割や可能性等について講話をいただきました。
講話後のWeb会議システムのグループミーティング機能を活用した受講者同士のグループ交流や質疑応答では、積極的な意見交流や情報交換が行われました。廣瀬氏からは、他地域の「先進事例」ではなく、地域の歴史を地域の高齢者から聞く「先人事例」により地域を理解し、学ぶ重要性や、学校運営協議会等の会議の場の盛り上げ方、温め方のコツの紹介といった、受講者の地域学校協働活動での困りごとに対する有益な助言が行われました。
受講者からは、質問だけでなく、廣瀬氏に自身の地域と学校の現状や課題を伝える場面もあり、双方向での学び合いの場となりました。
次回の育成研修は令和5年8月に実施する予定です。受講者が今回の育成研修で学んだことを生かし、それぞれの地域でより一層活躍されることを期待しています。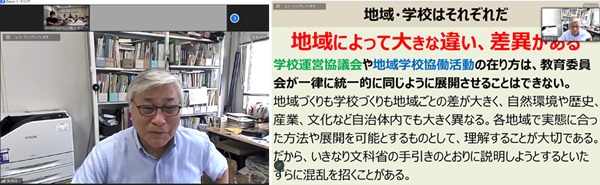
廣瀬隆人氏による講演の様子
育成研修(オンライン)の様子
大垣市「上石津地域学校協働活動本部設立準備プロジェクト会議(仮称)」の参加者を対象とした講演会を実施しました
令和5年6月27日に、上石津地域事務所において、大垣市「上石津地域学校協働活動本部設立準備プロジェクト会議(仮称)」の参加者を対象に「地域学校協働活動支援プログラム」を実施しました。講師は、岐阜小学校学校運営協議会長 青山朋宏氏です。講演会では、2つの小学校の統合時から現在に至るまでの、組織の変遷や合言葉の作成、非認知能力を育むために行う数々の活動の話が、講師のにこやかな笑顔とともに展開されました。上石津地域では、義務教育学校・上石津学園の開校を令和6年4月に控えており、参加者は、自分事として熱心に聞き入っていました。
参加者からは、「各地域の伝統を統合でどうしていったらよいのか」や「人が集まるワークショップにするにはどうしたらよいのか」など多くの質問がありました。「話し合う」ことの大切さや「大人が楽しむ」という心構えを学ぶことができました。
今後、上石津地域学校協働活動本部設立に向け、プロジェクト会議を重ねていく予定です。
瑞浪市「瑞浪市社会教育委員」を対象とした講演会を実施しました
令和5年6月21日(水)に瑞浪市総合文化センターで、第2回瑞浪市社会教育委員会定例会が開催され、社会教育委員10名が参加しました。
今年度の社会教育委員会の調査研究テーマは「瑞浪市地域学校協働活動の推進について」です。地域学校協働活動に関する共通認識を深めるため、ぎふ地域学校協働活動センターの「地域学校協働活動支援プログラム」による講演会を実施しました。
講師は高山市大八まちづくり協議会のコーディネーターで、大八まちづくり協議会の事務局として、高山市立東山中学校に常駐し、地域と学校の協働活動に精力的に取り組んでいる山本真紀氏です。
山本氏から、「高山市大八地区での地域学校協働活動について」というテーマで、学校運営協議会と地域学校協働活動の連携の仕方、手段ではなく目的を明確にした取組等について講演していただきました。さらに、実際に活動が始まると出てくる困り事に対する手立てや社会教育委員の役割等も学ぶ機会となりました。また、「かつて地域行事に参加した子どもが、成人して地域に戻り、講師として行事に参加してくれた喜び」や、「効果はすぐには出ない。試行錯誤を繰り返しながら、こつこつと続けていくしかない」といった点についてもお話があり、各社会教育委員が今実践していることへの後押しとなる講演会となりました。
定例会の後半は、調査研究する内容や各学校の学校運営協議会委員に実施するアンケート内容の検討が行われ、社会教育委員代表の有賀秀雄氏や副代表の伊藤孝一氏を中心に活発に意見交流が行われました。
「コミスクふるにし」サポーターズクラブを対象とした講演会を実施しました
令和5年6月17日(土)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである「講師派遣プログラム」を活用し、「コミスクふるにし」サポーターズクラブ交流会が開催されました。
飛騨市には8つの小中学校があり、令和2年4月より全ての学校にコミュニティ・スクールが導入されています。飛騨市立古川西小学校は、学校運営協議会、地域学校協働本部が既に組織されていますが、今回、校区内の様々な企業や地域ボランティア団体等で構成される「コミスクふるにし」サポーターズクラブを立ち上げ、講演会及び交流会を企画しました。
古田哲也氏(下呂市立小坂中学校教頭)を講師にお招きし、近隣地域の先進事例や地域の大人がそれぞれに自分事として捉え活動を行っていくことについてお話いただきました。
講演では、地域・家庭・学校の三者が連携・協働する要として「わがまち(願いの共有)」、「わがごと(当事者意識)」、「わがままに(連携・協働)」の3つの柱を紹介し、それぞれが役割と責任を自覚した「願いの生み出し」、「願いの検証」、「願いの評価」を行うことが大切であることを、事例を交えて紹介していただきました。講演後、参加者は5つの分科会に分かれて、それぞれの活動についての意見交換等の交流会を行いました。
参加者からは、「事例を知るだけではなく、この取組がどう未来の子どもたちへ繋がっていくかがよくわかる話で、これからの取組の参考になった」、「より自分たちが行ってきた活動が、古西校区にとっても、地域住民にとっても意味のあることに気付く機会にもなった」といった声が聞かれました。
この交流会を機に、古川西小学校の取組がさらに活発になり、地域全体で子どもたちを育む機運が高まることを期待しています。
令和5年度第1回地域学校協働活動推進員等フォローアップ研修を実施しました
令和5年6月20日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センター(岐阜県と岐阜大学による共同設置)の人材育成事業の一つである「地域学校協働活動推進員等フォローアップ研修」を実施しました。
受講者の皆さんは、昨年度までに「地域学校協働活動推進員等育成研修」を修了し、現在、県内各地域で、地域学校協働活動推進員や地域コーディネーター、社会教育行政・公民館関係者、教職員等として活躍されている方々です。今年度は46名の受講申込がありました。
今回は、文部科学省国立教育政策研究所の志々田まなみ氏を講師にお招きし、「地域学校協働活動におけるボランティア人材の確保・育成」について講話をいただきました。また、講話後の意見交換の場では、活動を充実させる働きかけやボランティアを楽しんでもらうための工夫について、質問や事例が共有されました。
受講者からは、「地域学校協働活動は学校の負担を増やすものと心配していたが、そうではないことがわかった」、「自分にできることから始めていきたい」、「子どもが誇りをもてる地域となるよう、仲間を増やして楽しみながら取り組んでいきます」といった前向きな感想が聞かれました。
次回のフォローアップ研修は令和6年1月となります。今回の研修で学んだことを生かし、それぞれの地域でご活躍いただけることを期待しています。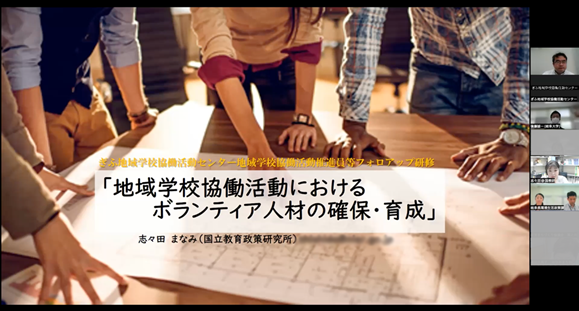
フォローアップ研修の様子