令和6年8月7日(水)、ぎふ地域学校協働活動センターの二村玲衣センター員が担当する講義の一環として、愛知県の蒲郡市立蒲郡南部小学校で実施された放課後子ども教室「読書感想文講座」に学生ボランティアを派遣しました。
「読書感想文講座」は2022年より、蒲郡市地域学校協働活動推進員の早川康子氏と山本紀代氏(元学校図書館支援員で講師を務める)が地域住民の要望に応え、地域の小学生を対象に実施されています。同校の卒業生が通う蒲郡市立蒲郡中学校の生徒・教員との連携、蒲郡中学校を卒業した高校生、教育関係者、児童・生徒の保護者や住民が協力し小学生の読書感想文を支援することが講座の主な内容であり、世代を超えた交流の場として機能してきました。
岐阜大学との協働は今年度が初の試みであり、当日は小学生13名、中学生8名、高校生8名と推進員等住民11名、蒲郡市学校教員5名と、岐阜大学から学生26名、教員1名が参加しました。加えて、昼食の調理スタッフとして地域住民13名の協力があり、同日は総勢85名が同講座に関わりました。
講座は、講師の山本氏や地域の住民、教員が見守るなか、小学生1人につき中学生・高校生・大学生が3〜4名ほどが付いてグループをつくり、大学生の進行のもと小学生に本の内容や感想をインタビューするかたちで進められました。内容や感想を掘り下げるなかで互いの思いや経験を伝えあうことで、次第に参加者間の交流が深められました。
例として、東日本大震災にかかわる本の感想文に取り組む小学生のグループでは、発災時まだ生まれていない小中学生に向け、地域住民の方から当時の蒲郡市の様子についてお話があったり、当時未就学児や小学生だった大学生が子どもとして震災をどう感じたかを伝えたりすることで、互いに震災への解像度を高めながら話し合える関係性を築いていく様子が見受けられました。
多くの小学生が午前中に感想文を完成させ、以降は多世代交流の時間となりました。昼食は日頃から「がまなん食堂」*に携わっておられる地域住民の方々が100人分のカレーを調理しご提供くださり、学生や地域の子どもたちが一緒になって話しながら美味しくいただきました。
その後は地域住民の方によるご指導のもとでお抹茶体験をしたり、自由にカードゲームをしたりと、世代を超えて楽しみあい、参加者間でさらに交流を深めました。
参加した学生からは、「イベントのように楽しみながら取り組めるので、読書感想文への苦手意識が解消されるのではと思った」、「人との新たなつながりを作れる上に楽しい思い出ができるので、また参加しようかな・今度は友達も誘ってみようと思える講座だと感じた」等、講座そのものの意義に対する感想や、「これまであまり経験したことのなかった地域の多世代との交流で心が温まり、こうした活動に今後も関わってみたいと思った」、「このような機会を地域と学校が協⼒して作ることで、地域にも良いことがあると思いました。実際に、私が担当した子も今後のボランティアに参加する予定があると聞きました。きっと地域の⽅と交流があるから、今後のボランティアにも参加しやすいのだなと思いました」等、こうした地域活動がもつ価値への気づきの声が聞かれました。
また、地域住民の方からは、「この地区では普段子どもたちが大学生と交流できる機会がほとんどないので、よい機会となった」、「たくさんお兄さんお姉さんがいることで、子どもが普段の活動以上に楽しそうでうれしくなった」、「感想文を書くときに大学生が教えてくれたことは、今はまだその子にはわからなくても、その感想文を読み返すとき、大人になって思い出したとき、自分が物を考えるとき、きっとその子の力になっていると思う」といったコメントをいただきました。
蒲郡南部地区では活発な地域学校協働活動が行われてきており、今後も引き続き講義等での関わりを続けていく予定です。ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後も蒲郡市をはじめとした岐阜県内外のさまざまな地域と関わりながら、よりよい地域学校協働活動のあり方について探究を進めていきます。
*蒲郡市内で地域活動を行う団体「小江まちカフェ」が主体となり、地域住民の協力のもと、蒲郡南部小学校の子どもを対象に実施している子ども食堂。

月別アーカイブ: 2024年9月
令和6年度第2回地域学校協働活動推進員等育成研修(全4回)を実施しました
令和6年8月27日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センターの人材育成事業の一つである「第2回地域学校協働活動推進員等育成研修」(以下、「育成研修」)をオンラインにて実施しました。県内各地域の社会教育行政、公民館等の施設、学校、地域団体等で活躍している55名が受講しました。
今回は、はじめに事例紹介として、岐阜市立岐阜小学校学校運営協議会会長の青山朋宏氏と高山市大八まちづくり協議会の山本真紀氏から講話をいただきました。
青山氏からは岐阜市立岐阜小学校における「ふるさと学習」を基盤とした学校・家庭・地域の協働による教育活動の実践について、山本氏からは「WIN-WINでつながる子どもを核とした地域づくり~地域コーディネーターの役割を考える~」と題し、高山市東山校区における多様な地域学校協働活動についてお話しいただきました。
その後、筑波大学准教授の上田孝典氏から「先進事例と推進員の使命や役割」について講評と講話をいただきました。
講評では、両事例が一般的な地域活動の担い手層である高齢世代のみならず、保護者などの現役世代を担い手として巻き込みながら実施している点に着目し、担い手という全国の地域に共通する課題を乗り越え、活動が地域に定着する段階へ到達しているというコメントをいただきました。つづく講話では、なぜ、今、社会に開かれた教育課程の実現が求められているかという問いを軸とし、学校と地域をめぐる議論のこれまでの経緯について、国や文部科学省の文書等をもとにたどりながら、協働が求められる背景や理由について詳細な説明がありました。その上で、学校と地域が互いを知り信頼しながら、WIN-WINの関係を意識して取り組んでいくことが持続的な連携につながっていくとお話しいただきました。
最後に、ブレイクアウトルーム機能を活用した参加者間での意見交換の時間を設けました。事例発表や講評を受けて各自の地域に照らし合わせたコメントが交わされ、各地区での活動の状況や課題などが共有されました。
それぞれの講話とブレイクアウトルームセッションの後に実施した質疑応答では、「活動に関わる地域住民や保護者をどのように集めているか」、「担い手の役職はずっと同じ人が担ってもよいのか、ローテーションさせるべきか」、「学校の授業時間を活用する際には、時間数や内容などどのように決めているか」、「子どもや大人が活動に対して主体的に取り組めるようにするコツは何か」といった実践的な方法に関する質問や、「実践が周辺地域の校区や学校に影響していることはあるか」、「どのように活動することで、地域の中のゆるやかなつながりを作れるのだろうか」といった活動外への波及効果を尋ねる質問等があり、講師―参加者間で活発な意見交換がなされました。
次回の育成研修は令和6年10月1日(火)に実施します。ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後も研修事業等を通じ、地域学校協働活動にかかわる方々を対象とした学びや情報共有の場を提供していきます。
青山氏による事例紹介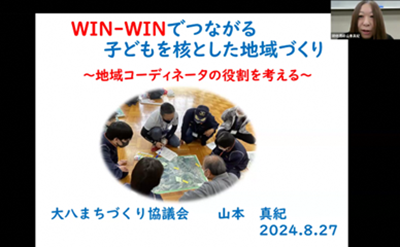
山本氏による事例紹介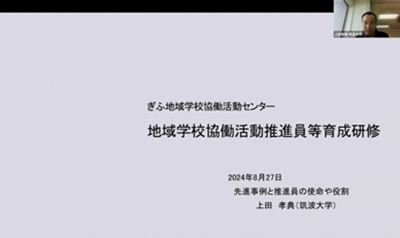
上田氏による講評と講話
令和6年度「コミュニティ・スクール 地域学校協働活動」研修会を実施しました
令和6年7月23日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センターの人材育成事業の一つである「コミュニティ・スクール 地域学校協働活動研修会」をオンラインで実施しました。県内各地域の学校教職員、社会教育行政等で活躍している方々など350名の受講がありました。
研修会ではまず、岐阜県県民生活課課長補佐の永田千奈津氏による岐阜県のコミュニティ・スクール、地域学校協働活動に関する施策説明がありました。その後の講演では、文部科学省CSマイスター、DX戦略アドバイザー、青森県教育改革有識者会議副議長 森 万喜子氏を講師に迎え「子どもの学びと育ちを、ともに支える ~子どもが主語の学校と温かい地域づくり~」をテーマにご講演をいただきました。参加者の感想の一部を紹介します。
○聞いたことはあるけれど分からなかった言葉のイメージが具体化しました。
○CSを自由な熟議にしていくことは大変おもしろそうだと感じました。
○「やってみる」「巻き込んでいく」「助け(協力)を求める」が大切だと感じました。
○メンバー選考は多様性を重視し、様々な人の対等な話し合いが必要だとわかりました。
○一時的な大変さがあっても熟議することで子どもがいきいき学べる環境がつくれるのだと思います。
○一番近い学校を一番よい学校にするためにCSの在り方を模索したいです。
講師の豊富な実践に裏打ちされた理論とアイデアあふれる具体事例の紹介により、参加者がコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進についての理解を深め、自校や地域での今後の活動の見通しをもつよい機会となりました。
ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後も人材育成事業等を通じて、地域学校協働活動を支援する取り組みを進めていきます。
永田千奈津氏による施策説明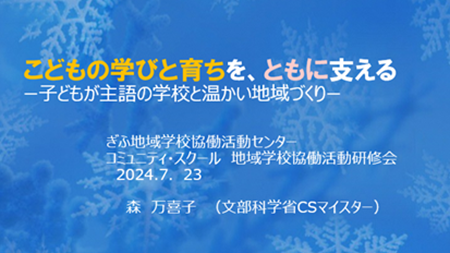
森 万喜子氏による講演