令和6年1月30日(火)、ぎふ地域学校協働活動センター事業のひとつである市町村支援プログラムに基づき、岐南町立東小学校の学校運営協議会へ講師派遣を行いました。今回の本協議会は羽島郡二町教育委員会と岐南町によって行われたもので、町内若手教員の校内研修の一環としても位置づけられ、10名の若手教員が参加しました。他にも学校運営協議会委員、地域学校協働活動推進員、教員、PTA関係者、教育行政関係者が参加し、参加者は計34名でした。
講師である岐阜市立岐阜小学校 学校運営協議会会長 青山朋宏氏からは、「地域学校協働活動の意義と推進について」と題し、地域学校協働活動の活性化について先進事例を交えながら掘り下げた講演がありました。
参加者からは、「今回の研修を経て、学校運営協議会の委員として、自分でも地域と学校をつなぐ活動を何か考えてみたいと思った。例えば、学校課題の一つである支援を必要とする児童への対応を何かやってみたい」といった前向きな感想が聞かれた他、研修の一環として若手教員が参加したことについて、「若い教員に地域と学校との連携に関心をもたせようと仕向けたことは、新しい試みとして意味があると感じた」といった声が聞かれました。
ぎふ地域学校協働活動センターでは、研修活動や相談支援活動を通じ、今後も岐阜県内各市町村に対し地域学校協働活動を支援する取り組みを進めていきます。
カテゴリー別アーカイブ: 報告
学生ボランティアを紹介した冊子が岐阜新聞で紹介されました
令和6年3月6日(水)の岐阜新聞朝刊に、岐阜県社会教育委員の会が作成した「進めよう!地域学校協働活動 Vol.2」を紹介する記事が掲載されました。同記事の写真には、ぎふ地域学校協働活動センター センター長の益川浩一と、学生ボランティアとして活躍する教育学部の森本圭祐さんが写っています。
同冊子は、地域学校協働活動の概要や岐阜県の現状、協働活動を支える人々を紹介したものです。協働活動を支えるひとつのアクターとして、ぎふ地域学校協働活動センター事業の「学生ボランティア派遣」で活躍している学生ボランティアが紹介されています。
ぎふ地域学校協働活動センターは、学生ボランティア派遣も含め、今後もさまざまな形で地域支援を実施し、地域学校協働活動を推進していきます。
海津小学校運営協議会設置委員会にて市町村支援プログラムを実施しました
令和6年2月22日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業のひとつである市町村支援プログラムに基づき、海津市教育委員会社会教育課が主催する第4回海津小学校運営協議会設置委員会へ講師派遣を行いました。
本委員会には教育行政職員、市内学校長、PTA関係者、社会福祉協議会等の福祉や青少年育成の関係者、計21名が出席しました。今回の講師派遣は、講演を通して学校運営協議会の今後の動きについて学び、地域とともにある学校づくりにつなげるため実施されました。
講演では、岐阜大学教授・ぎふ地域学校協働活動センター センター長 益川浩一が講師を務め、学校運営協議会を設置することの利点や実施状況、地域学校協働活動を充実させていくことの必要性について話しました。
講演後の意見交換も活発に行われました。例えば、「学校が統合するにあたり、5つのコミュニティと1つの学校がどうかかわっていくとよいか」という質問に対し、講師からは、「各地区で培われてきたものを大切にしながら、そこに関わることができる存在として子どもたちが加わるのだ、というプラスの視点で考えるとよい」と活動に対する視点にかかわらせた助言がありました。
終了後、参加者からは「運営協議会委員の役割、そして地域としてどのように学校として関わっていくとよいか、具体的な例を出してもらえてよくわかった」といった声が聞かれました。
ぎふ地域学校協働活動センターでは、次年度以降も当プログラム等を活用し、様々な活動に取り組んでいく予定です。
令和5年度岐阜県地域学校協働活動フォーラム2023を実施しました
令和6年2月27日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センターの1年間の成果報告および学び合いの機会である「岐阜県地域学校協働活動フォーラム2023」をオンラインで実施しました。
ぎふ地域学校協働活動センターは、地域・自治体・学校における地域学校協働活動を支援・促進し、子どもたちの成長を地域全体で支えるとともに、活動を通じて地域の活性化を図ることを目的に、岐阜県と岐阜大学によって共同で設置されました。
同センターでは、下記3つの柱を中心に事業を実施しています。
1.人材育成・確保(市町村や社会教育関係団体と連携し、地域学校協働活動推進員(コーディネーター)などを育成する研修や、学生ボランティアの育成・確保)
2.調査研究(市町村や社会教育関係団体と連携し、協働活動や家庭教育等の先進性・モデル性のある実践事例等の調査研究を実施し、発表・報告)
3.普及促進(出前講義やワークショップに参画するなど市町村における推進体制づくりを支援するとともに、実践活動の促進に向けた普及イベント等を開催)
「岐阜県地域学校協働活動フォーラム」は、地域学校協働活動関係者(社会教育委員、社会教育士、公民館職員、地域学校協働活動推進員、青少年育成関係者、まちづくり協議会関係者、地域づくり関係者等)、市町村等行政職員、学校関係者(教職員、学校運営協議会委員等)を対象に、地域学校協働活動にかかわる学術的知見や岐阜県内における実践の情報を共有する目的で行われているものです。
今年度の参加申込者は244名で、岐阜県内各地域において活躍している地域学校協働活動関係者、市町村等行政職員、社会教育行政職員、学校関係者等に参加していただきましたが、特に校長・教頭といった学校管理職の方々が多く参加され、学校現場での関心の高さが感じられました。
今回は、東京大学大学院教育学研究科教授・文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会社会教育人材部会長 牧野篤氏から、「『ふるさと』をつくる―地域社会と学校の連携・協働を考える―」と題した講演をいただきました。社会的背景を踏まえ、社会教育にかかわる今日の政策を読み解きながら、一緒に「在る」関係性を実現しつつ地域社会と学校が協働していくための視点についてお話いただきました。
続いて、実践紹介として、郡上市立大中(おおなか)小学校校長 山下哲男氏・教頭 横山亜希氏から「地域(人、もの、こと)のよさに気付き、ふるさとを大切に想う子の育成―地域の人やその思いに触れる協働的な学びを通して―」と題する報告をいただきました。大中小学校におけるコミュニティ・スクールの取り組みとして、地域から理解や協力を得るために行った活動、連携組織や具体的な協働活動の実際についてお話いただきました。
講演・報告の後には、質疑応答の時間を設けました。地域住民と連携する上で気をつけること、幼保等機関と小学校の連携、活動実施における推進員の働き等、さまざまな角度から寄せられた質問によって、講演・報告を掘り下げることができました。
最後に、岐阜大学教授・ぎふ地域学校協働活動センター長の益川浩一がセンターの一年間の活動成果を報告し、フォーラム全体を総括して閉会しました。
ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後もこうしたフォーラムや研修会等を開催し、地域学校協働活動に関する普及促進活動を図っていきます。
牧野氏による講演の様子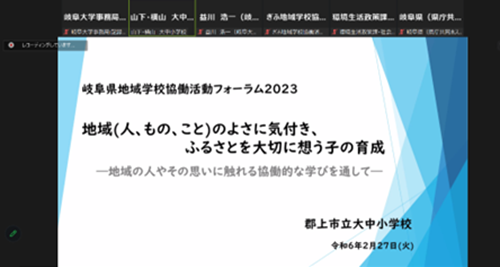
大中小学校による報告の様子
地域協学センター益川教授が社会教育功労者表彰を受賞しました
本学地域協学センター益川教授が令和5年度社会教育功労者表彰(文部科学大臣表彰)を受賞しました。
この表彰は、地域における社会教育活動を推進するため多年にわたり社会教育の振興に功労のあった者、及び全国的見地から多年にわたり社会教育関係の団体活動等に精励し社会教育の振興に功労のあったものに対し、その功績をたたえるものです。益川教授は岐阜県社会教育委員の会議長を長年務めるなど、地域における社会教育振興の功労が認められたため受賞となりました。
2月19日(月)には、今回の受賞について益川教授が吉田学長へ報告を行いました。
益川教授は、「岐阜大学に育てていただき、社会教育に関する教育研究活動に邁進できたことが今回の受賞につながったと思っている」と受賞について語りました。吉田学長からは、「これからも自治体との連携を続けていっていただきたい」と激励しました。
本学は引き続き、地域活性化の中核拠点を目指していきます。 
学長報告の様子 
記念撮影
令和5年度地域学校協働活動推進員等フォローアップ研修(第2回)を実施しました
令和6年1月25日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センターの人材育成事業の一つである「地域学校協働活動推進員等フォローアップ研修」を実施しました。
ぎふ地域学校協働活動センターは、地域・自治体・学校における「地域学校協働活動」を支援・促進し、子どもたちの成長を地域全体で支えるとともに、活動を通じて地域の活性化を図ることを目的に、岐阜県と岐阜大学によって共同で設置されました。
同センターでは、
1.人材育成・確保(市町村や社会教育関係団体と連携し、地域学校協働活動推進員(コーディネーター)などを育成する研修や、学生ボランティアの育成・確保)
2.調査研究(市町村や社会教育関係団体と連携し、協働活動や家庭教育等の先進性・モデル性のある実践事例等の調査研究を実施し、発表・報告)
3.普及促進(出前講義やワークショップに参画するなど市町村における推進体制づくりを支援するとともに、実践活動の促進に向けた普及イベント等を開催)
を行っています。
同研修は、地域学校協働活動推進員等育成研修を修了後、県内各地域の社会教育行政、公民館等の施設、学校、地域団体等で活躍されている方を対象に、より深い地域学校協働活動の理解を促すことを目的とした、発展的な学びや情報共有の場です。今年度は46名の受講申込がありました。
今回は、前半で瑞浪市教育委員会学校教育課 統括コーディネーター 吉村美信氏から「行政関係課の連携」と題した講演をいただきました。具体的には、地域学校協働活動を推進するために統括コーディネーターとしてどのように行政関係課や地域のアクターへ働きかけているか、ご自身の経験や現在の取り組みをもとにお話しいただきました。質疑応答では、吉村氏が実践されている行政関係課との橋渡しの取り組み、まちづくり組織のスムーズな運営等について活発な情報交換が行われました。
後半では、受講者間でKJ法を用いたグループワークを行い、受講者がそれぞれの実践で苦労していることや悩んでいることを共有するとともに、改善や解決のための方策を検討しました。最後に、各グループからの発表を通じて、話し合われた内容を全体へ共有し、研修を終えました。
フォローアップ研修は今回で終了となりますが、これまでの研修で学んだことを生かし、それぞれの地域でご活躍いただけることを期待しています。
吉村美信氏による講演の様子 グループワークの様子
羽島市立中央小学校の放課後子ども教室へ学生ボランティアを派遣しました
令和5年12月15日(金)、ぎふ地域学校協働活動センター事業のひとつである学生ボランティアマッチング機能を活用し、岐阜大学の学生ボランティア3名(地域科学部1年生1名、同学部2年生2名)が羽島市立中央小学校の放課後子ども教室に参加しました。今回の子どもの参加数は10名で、地域の有志ボランティアからなる支援員4名、ボッチャの外部講師2名とともに活動を行いました。
羽島市立中央小学校の放課後子ども教室では、地域の有志ボランティアが支援員となり、小学校3年生を対象に、軽スポーツや伝統文化などの体験活動を実施しています。
今回の活動内容は、ボッチャ体験でした。学生ボランティアは子どもたちとともにボッチャを体験しながら、子どもたちが楽しく活動できるように声掛けやボール回しをしました。
参加した学生ボランティアは、「支援員の方を見ていて印象に残ったことは、子どもと接する際に気を使いすぎず自然体で子どもと接していて、子どもたちも親しみやすい様子だった」、「支援員が見守る様子を見て、子どもと接する際に必要なことを学ぶことができた」、「子どもたちにとって、自分たちのことをよく見てくれていて、声をかけてくれる大人がいるというこの放課後子ども教室は、家や学校とは違った子どもたちにとっての居場所になっていると実感した。それは、周りの大人たちの努力によって成り立っているものであるので、居場所があるという雰囲気を作り出せる支援員の方の行動は素晴らしいと思った」と、子どもに接する支援員の姿から学びを得ることができ、それぞれに支援のあり方を考えていました。
ぎふ地域学校協働活動センターでは、引き続き学生ボランティアによる支援を促す取り組みを進めていきます。
美濃市地域学校協働活動研修会にて市町村支援プログラムを実施しました
令和5年12月13日(水)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業のひとつである市町村支援プログラムに基づき、美濃市教育委員会主催の美濃市地域学校協働活動研修会へ講師派遣を行いました。
美濃市では地域学校協働活動本部の設置を進めており、本研修会は関係者や市民に地域学校協働活動本部や同活動について理解を深めてもらうことを目的として実施されました。参加者は、教育委員会職員、コミュニティスクール委員、学校教員、社会教育委員、放課後子ども教室支援員、公民館長、市議会議員等、計45名でした。
講師は岐阜大学教授・ぎふ地域学校協働活動センター センター長の益川浩一が担当し、「地域と学校の連携・協働で子どもの学び・育ちを支え、地域づくりを進める」を演題として地域学校協働活動について講演しました。
参加者からは、「地域と学校の連携を大切に、今あるものを活かすことを進めながら、お互いに協力し合って実践できると良いと思う」、「『今あるものを活かす』、『子どもの意見を聞く』、『願いを共有する』、『活動を知ってもらい仲間をふやす』等、ヒントをいただきました」等、地域学校協働活動を進めていく土台となる発想や考えを得られたという感想が多く聞かれました。
ぎふ地域学校協働活動センターでは、研修活動や相談支援活動を通じ、今後も岐阜県内各市町村に対し地域学校協働活動を支援する取り組みを進めていきます。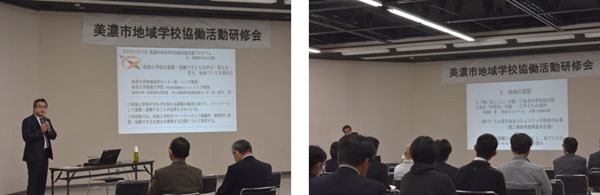
各務原市立蘇原中学校「蘇中塾」において学生ボランティアによる学習支援を実施しました
令和5年12月13日(水)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業のひとつである学生ボランティアマッチング機能を活用し、岐阜大学の学生ボランティア2名(社会システム経営学環2年生1名、教育学部3年生1名)が各務原市蘇原中学校「蘇中塾」にて学習支援を実施しました。この日は参加生徒14名に対し、中学校教員5名とともに支援にあたりました。
蘇原中学校では、放課後に「個性の伸長・自己決定力・コミュニケーション力等の育成」を目的として、さまざまな講座を中学生に提供する「アフタースクール」を提供しており、「蘇中塾」はその一講座です。「蘇中塾」は、学習においてわからないことがある、困っているという生徒を対象に、基礎基本の問題から発展的な問題まで丁寧に教える場です。学生ボランティアは中学生と一つのテーブルを囲み、中学生の質問に答えたり、つまづきに対してヒントを与えたりしながら学習を支援しました。
参加した学生ボランティアは、「生徒に助言をするなかで、うまくできた部分もあれば反省する部分もあり、生徒の疑問や声に耳を傾け、とことん向き合う姿勢は、いつなんどき忘れてはならないと感じた」、「参加した生徒の中には、初歩的な部分でつまづいている子もおり、そのような生徒の理解を支えるためにも蘇中塾は大きな役割を果たしていると感じた」と、それぞれに活動から学びを得ていました。
ぎふ地域学校協働活動センターでは、引き続き学生ボランティアによる支援を促す取り組みを進めていきます。
羽島市立足近小学校の放課後子ども教室へ学生ボランティアを派遣しました
令和5年12月7日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである学生ボランティアマッチング機能を活用し、岐阜大学の学生ボランティア(地域科学部2年生3名)が羽島市立足近小学校の放課後子ども教室に参加しました。今回の子どもの参加数は12名で、地域の有志ボランティアからなる支援員4名、講師役の足近グラウンドゴルフクラブの方々6名とともに活動を行いました。
足近小学校の放課後子ども教室では、地域の有志ボランティアが支援員となり、小学校3年生を対象に、軽スポーツや伝統文化などの体験活動を実施しています。
今回の放課後子ども教室では、グラウンドゴルフ体験をした後、自主学習に取り組みました。体験の際は、足近グラウンドゴルフクラブの方々が講師役となり、子どもたちとふれあいながらグラウンドゴルフを楽しみました。学生ボランティアは子どもたちと一緒に体験しながら、子どもたちがルールを守りながら活動を楽しめるよう支援しました。また、自主学習の際には、宿題に取り組む子どもたちを見守り、集中して学習に取り組めるよう必要に応じた援助を行いました。
参加した学生ボランティアは、「支援員の声掛けや指導も、子どもたちの意欲が出るように工夫されており、子どもたちに嫌そうな顔をする子はおらず、みんな楽しく活動ができていました」、「支援員の励ましや誉め言葉があったことで子どもたちは自分に自信を持て、楽しくプレーをできたのだと思います」、「どんなに小さいことでも褒めることで子どもたちのやる気や参加しようという気持ちを高めたり、他にも、全体に声をかけるときは、大きな声でゆっくり、はっきりと聞こえやすいように声掛けをしていたが、子ども達が宿題をしているようなときには、寄り添って、そっと声掛けをするように、その場その場での対応が実践されており、子どもたちの立場に寄り添って考えることは大切だと実感した」と、支援員の子どもに対する声かけに工夫を感じ、支援のあり方について学んでいました。
ぎふ地域学校協働活動センターでは、引き続き学生ボランティアによる支援を促す取り組みを進めていきます。